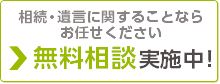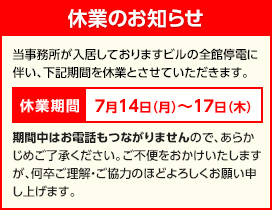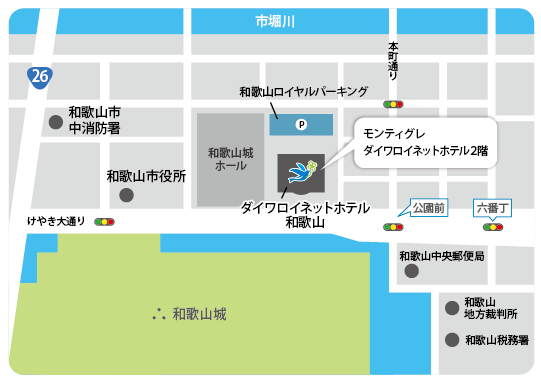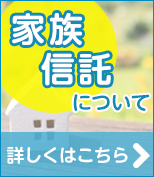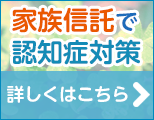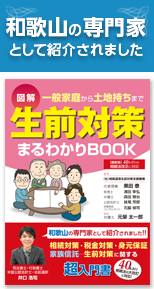遺留分侵害額の請求とは
遺言書を生前に作成しておけば、遺産を引き継ぐ人や相続財産の分け方などを指定をすることが可能です。相続人以外の人に遺産を分けたいという希望も叶えられます。
しかし、被相続人の配偶者や子など生活を共にしていた相続人によっては、その相続財産が無いと生活していけなくなるケースも存在します。
そのような相続人の生活を守るために、法律では遺留分という制度を定めています。遺留分とは一定の法定相続人が最低限取得ができる遺産の割合のことです。遺言書の内容に関わらず保障されます。
遺留分の割合は下記のようになります。
①.相続人が配偶者・子のどちらか一方でもいる場合、法定相続分の2分の1
②.相続人が直系尊属のみの場合、法定相続分の3分の1
③.兄弟姉妹の場合、遺留分はありませんので注意が必要です。
遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害されている相続人は、法定相続分よりも多くの財産を受け取っている法定相続人に対して、あるいは受遺者等に対してその侵害額(遺留分にあたる部分)を金銭で渡すように請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。 遺留分が侵害されている者は、その本人が遺留分侵害額の請求をして、はじめて遺留分を取り戻すことが可能です。つまり、遺留分侵害額の請求をしなければ、遺贈などにより財産を受け取った者がそのままその財産を取得してしまいますので、確実な意思表示が必要になります。
遺留分侵害額請求権の行使方法
遺留分侵害額請求権の行使方法は、特に手続きや特別なルールはありません。まずは相手に「遺留分を請求する」という意思を伝えることから始めます。
大まかな流れとしては遺留分侵害額請求の通知書を送ります。その際には証拠として残せるように内容証明郵便で郵送するのが一般的です。意思表示は相手方に到達された際に効力が生じますが、内容証明郵便による意思表示は社会通念上、受遺者に了知可能な状態に置かれたとして、留置期間が満了した時点で受遺者に到達したと認めたケースもあります。
その後、遺留分を侵害している受遺者や相続人と話し合いを進めていきますが、個人的な話し合いが難しい際には、家庭裁判所にて調停手続きを行うことも可能です。
裁判手続きでの請求では調停と訴訟があります。調停での話し合いがまとまらなかった時には訴訟を提起することになります。一般の民事事件となりますので行うのは地方裁判所です。なお、遺留分に関する事件は、調停制度のある家庭に関する事件であり調停前置主義がとられていますので、いきなり訴訟を提起することはできません。
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときや相続開始から10年が経過したときにも消滅しますので注意が必要です。
遺留分とは?について
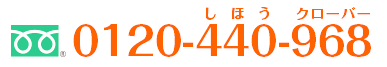
- 代表司法書士・行政書士 井口 浩司の地域密着宣言!
- 詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました
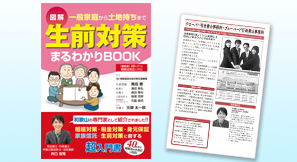
当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。